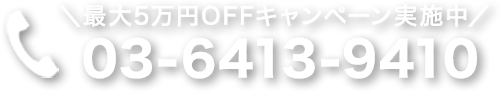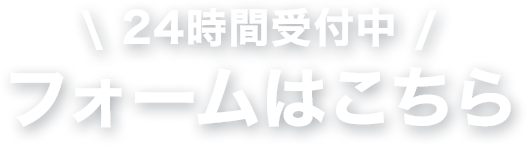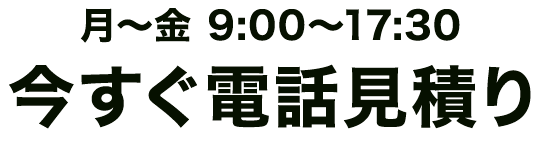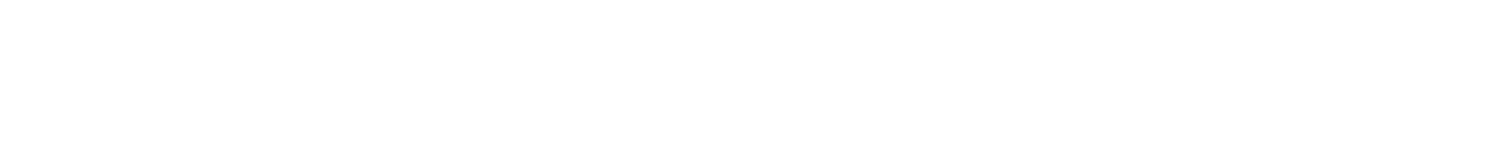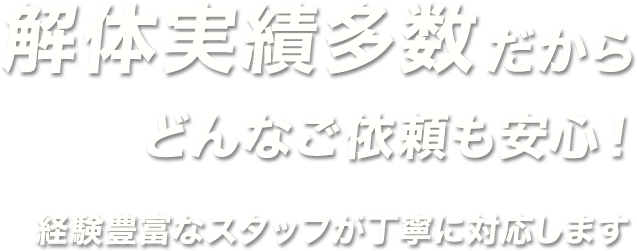【2025年最新版】ブロック塀・擁壁の部分解体費用と安全基準を徹底解説|見積チェックと補助金活用ガイド
この記事の要点・結論
ブロック塀や擁壁の部分解体は、単に壊すだけの作業ではありません。残存部分の安全性を確保し、法令を遵守した上で、適切な費用で実施する必要があります。本記事では、2025年最新の基準に基づき、費用内訳、安全基準、行政手続きから近隣対応まで、施主が知るべき全知識を網羅的に解説します。これにより、読者は見積書の妥当性を判断し、トラブルを未然に防ぐことができます。
結論:費用=工種×現場条件×安全措置。基準順守と仮設が最優先です
- 部分解体において最も重要なのは、残存部の安定性確保と、擁壁の場合は背後の土圧管理です。これらを怠ると、倒壊事故や再施工につながる危険があります。
- 見積書を評価する際は、単価だけでなく「どのような工法で、どのような安全対策(仮設)が含まれているか」を確認することが不可欠です。工種別の内訳と安全仮設費の有無が、優良な業者の見極めポイントとなります。
- 本記事で紹介する料金、規格、法令、補助金制度は、根拠となる「年月+出典名」を明記し、公式サイトへリンクしています。必ず最新情報をご確認ください。
用語と範囲の定義
部分解体の計画を立てる前に、対象となる「ブロック塀」と「擁壁」の基本的な違いを理解しておくことが重要です。これらは似て非なるもので、求められる安全基準や解体方法が大きく異なります。
ブロック塀と擁壁の違い
| 用語 | 意味 | 主な対象材 | 注意点 | 関連基準・法令 |
|---|---|---|---|---|
| ブロック塀 | コンクリートブロックを積み上げて造る塀。 | コンクリートブロック、鉄筋 | 主に隣地との境界設定や目隠しが目的。構造的な強度は擁壁に劣る。 | 建築基準法施行令第62条の8 |
| 擁壁(ようへき) | 高低差のある土地で、土が崩れるのを防ぐ壁。 | 鉄筋コンクリート(RC)、コンクリート | 背後から常に土圧がかかるため、構造計算に基づいた強固な設計と排水機能が不可欠。 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 |
※ブロック塀は主に視線を遮るための構造物ですが、擁壁は高低差のある地盤の崩壊を防ぐための土留め機能を持ちます。擁壁には背面の水を抜くための水抜き穴や、強度を補う控え壁、構造全体を支える基礎が一体となって機能しており、部分的な解体には細心の注意が必要です。
部分解体が必要になる典型ケース
ブロック塀や擁壁の全体を撤去するのではなく、一部分だけを解体する背景には様々な目的があります。ここでは、代表的なケースとその際に優先すべきリスク対策を解説します。
| ケース | 目的 | 優先すべきリスク | 必要な措置 | 代替案の例 |
|---|---|---|---|---|
| 倒壊危険の除去 | ひび割れや傾きがある危険な部分のみを撤去し、安全を確保する。 | 解体作業中の不意な倒壊、残存部分の強度低下。 | 支保工(サポート)による残存部の補強、作業範囲の立入禁止措置。 | 既存塀の補強・改修 |
| 道路後退(セットバック) | 建築基準法に基づき、敷地境界を後退させ、道路幅を確保する。 | 解体後の境界線の明確化、残存部の仕上げ。 | 正確な測量、残存部のモルタル補修や塗装。 | 塀全体の移設 |
| 開口部の拡幅 | 駐車スペースの出入口や門扉を広げ、利便性を向上させる。 | 開口部上部の崩落、残存部の垂直・水平の維持。 | カッター等による精密な切断、切断面の補強。 | 既存門扉の変更 |
| 越境状態の是正 | 隣地に越境している部分を解体し、境界問題を解決する。 | 隣地への粉じん・騒音、境界の最終確認。 | 隣地所有者との事前協議、養生シートの設置。 | 土地の分筆・売買 |
費用の考え方:内訳と増減要因
部分解体の費用は、単純な面積や長さだけでは決まりません。現場の状況に応じて様々な追加費用が発生するため、見積書の内訳を正しく理解することが重要です。
主要な工種と単価の目安
| 工種 | 範囲/数量 | 目安単価 | 増額条件 | 備考(含む/含まない) |
|---|---|---|---|---|
| ブロック塀解体 | 1平方メートルあたり | 5,000~10,000円/㎡ | 手壊し作業の比率が高い、鉄筋が多い、高さがある。 | 廃材処分費を含む場合が多い。 |
| 擁壁解体(RC) | 1平方メートルあたり | 14,000~35,000円/㎡ | 鉄筋が太い・多い、コンクリート強度が高い、厚みがある。 | 廃材処分費は別途の場合が多い。 |
| カッター切断 | 1メートルあたり | 3,000~8,000円/m | 切断する厚みが増す、ダイヤモンドブレードの消耗。 | 残存部をきれいに仕上げる場合に選択。 |
| 廃材運搬・処分 | 1立方メートルまたはトンあたり | 15,000~25,000円/㎥ | 処分場までの距離が遠い、分別が困難な混合廃棄物。 | コンクリートがら、鉄くずなど。 |
| 仮設・養生費 | 一式 | 30,000~100,000円/式 | 隣家との距離が近い、前面道路が狭い、防音パネルが必要。 | 足場、養生シート、防音シート等。 |
| 交通誘導員 | 1人1日あたり | 15,000~20,000円/人日 | 前面道路の交通量が多い、作業時間が長時間に及ぶ。 | 道路使用許可が必要な場合に必須。 |
※上記単価は2025年8月時点の一般的な市場価格です。出典:外構・エクステリアパートナーズ (2025年3月)、解体ガイド (2022年11月)。費用は重機の搬入可否(大型重機が使えない現場は手壊しとなり割高)、前面道路の幅(狭いと小型車両での搬出となり運搬回数が増加)、近隣との距離(養生がより厳重になる)など、現場固有の条件で大きく変動します。
安全基準・法令と確認フロー
ブロック塀や擁壁の解体は、人命に関わる重大な事故につながる可能性があるため、様々な法律で安全基準が定められています。発注者としても、業者がこれらの法令を遵守しているかを確認する責任があります。
遵守すべき主要法令一覧
| 区分 | 要点 | 適用条件 | 根拠(年月+出典名) |
|---|---|---|---|
| 建築基準法 | 塀の高さ、厚み、控え壁の設置、基礎の構造などが規定されている。特に高さ1.2mを超える塀は厳格な基準が適用される。 | 新設・改修時だけでなく、既存不適格の塀を安全点検する際の基準となる。 | 2018年6月 国土交通省 国住指第1130号 |
| 宅地造成及び特定盛土等規制法 | 高さ2mを超える擁壁の設置・撤去や、大規模な盛土・切土を伴う工事は、都道府県知事の許可が必要になる場合がある。 | 宅地造成工事規制区域内での工事。 | 2023年5月 国土交通省 盛土規制法 |
| 労働安全衛生法 | 解体作業時の危険防止措置(作業計画の作成、立入禁止区域の設定、足場・支保工の設置基準など)を定めている。 | 全ての解体工事作業者および事業者に適用。 | 令和4年度 国土交通省 建築物解体工事共通仕様書 |
| 石綿障害予防規則(石綿則) | 解体対象物にアスベスト(石綿)が含まれているか否かの事前調査を義務化。床面積80㎡以上等の解体工事は、調査結果の電子報告が必要。 | 原則として全ての解体・改修工事。 | 2025年7月 厚生労働省 石綿事前調査結果報告システム |
| 建設リサイクル法 | コンクリートがら等の特定建設資材を分別し、再資源化することを義務付けている。対象工事は7日前までに都道府県への届出が必要。 | 請負金額500万円以上の解体工事など。 | 国土交通省 建設リサイクル法 |
| 騒音・振動規制法 | 指定された重機を使用する作業(特定建設作業)は、作業時間帯、日数、騒音・振動の大きさが制限される。 | 住宅地など(第1号区域)では、作業は原則午前7時~午後7時まで。 | 2025年7月 神奈川県 特定建設作業 |
※これらの法令は相互に関連しており、複数の手続きを同時に進める必要があります。例えば、建築基準法で危険と判断されたブロック塀の撤去工事では、労働安全衛生法に基づいた安全計画を立て、建設リサイクル法に従って廃材を処理し、騒音規制法を守りながら作業を進めなければなりません。
工法比較と選定
部分解体で重要なのは、残したい部分にダメージを与えず、騒音や粉じんを最小限に抑えることです。現場の条件に適した工法を選ぶことが、仕上がりの品質とコスト、安全性を左右します。
代表的な部分解体工法
| 工法 | 向いている条件 | 騒音/粉じんレベル | 精度/速度 | 留意点 |
|---|---|---|---|---|
| ハンドブレーカー(はつり) | 小規模な解体、重機が入れない狭い場所、不整形な箇所の解体。 | 大 / 大 | 低 / 遅 | 振動が大きく、残存部に影響を与える可能性。散水が必須。 |
| コンクリートカッター | 直線的な切断、開口部の設置、縁石の切断など、きれいな切断面が必要な場合。 | 中 / 少 (湿式) | 高 / 中 | 切断時の冷却水(汚泥)の処理が必要。厚みのある壁には不向き。 |
| ウォールソー | 鉄筋コンクリート擁壁など、厚く大規模な壁体を高精度で切断する場合。 | 中 / 少 (湿式) | 高 / 速 | 機械の設置スペースが必要。専門性が高く、費用は比較的高価。 |
| ワイヤーソー | 非常に厚い壁、複雑な形状、低騒音・低振動が求められる場所での切断。 | 小 / 少 (湿式) | 高 / 中 | ワイヤーを通すためのコア抜き(穴あけ)作業が別途必要。 |
土圧・崩壊防止の仮設と排水
特に擁壁の部分解体では、背後からの土圧によって残存部分が崩壊するリスクを常に考慮しなければなりません。安全確保の要となるのが、仮設の支保工と排水措置です。
安全を確保するための仮設・措置
- 支保工(しほこう)の設置:残存する壁や背後の土砂が崩れないように、単管パイプや角材などで一時的な支持構造物を組み立てます。これは、労働安全衛生法でも定められた重要な措置です。 [1]
- 背面の排水(水抜き)確保:解体作業によって既存の水抜き穴が塞がると、壁の背面に水圧がかかり、倒壊のリスクが急激に高まります。作業中は仮の排水経路を確保し、絶対に水を溜めないように管理します。
- 雨天時の作業中止:雨が降ると土の含水率が上がり、土圧が増大します。安全管理計画に基づき、一定の降雨量を超えた場合は作業を中断する判断が求められます。
キャプション[1]:根拠資料: 労働安全衛生規則解説(建設物価調査会)、発行年月: 令和5年頃、URL: https://www.kensaibou.or.jp/safe_tech/regulations/files/official_regulations_explanation_11.pdf
近隣対応と許認可・届出
解体工事は騒音、振動、粉じんの発生が避けられず、近隣トラブルの原因となりやすい作業です。円滑に工事を進めるためには、法的な手続きと並行して、誠実な近隣対応が不可欠です。
主な手続きと対応事項
| 行為 | 必要書類/許可 | 所管 | 提出時期の目安 | 現地での対応 |
|---|---|---|---|---|
| 事前挨拶 | 工事概要説明書、工程表、連絡先一覧 | (自主対応) | 着工の1週間前まで | 両隣、向かい、裏の家などへ直接訪問し説明。 |
| 道路の使用 | 道路使用許可申請書 | 所轄警察署 | 着工の1〜2週間前 | 許可証の現場掲示、交通誘導員の配置。 |
| 特定建設作業 | 特定建設作業実施届出書 | 市区町村の環境担当課 | 作業開始の7日前まで | 作業時間・曜日の遵守、低騒音型重機の使用。 |
| 粉じん対策 | (仕様書・計画書に記載) | (自主管理) | 常時 | 養生シートの設置、定期的な散水。 |
| 苦情対応 | 対応記録簿 | (自主対応) | 発生時、即時 | 現場責任者の連絡先を掲示し、誠実に対応する体制を構築。 |
※道路使用許可については道路交通法第77条で定められており、無許可で作業を行うと罰則の対象となります(2025年5月時点、株式会社エコ・プラン)。
産廃処理と再資源化
解体工事で発生したコンクリートがらや鉄くずは、産業廃棄物として法律に基づき適正に処理しなければなりません。不法投棄は排出者(施主)にも責任が問われるため、処理フローを理解しておくことが重要です。
品目別の処理方法と費用
| 品目 | 区分 | 処理費の目安 | 処理フローと注意点 |
|---|---|---|---|
| コンクリートがら | 産業廃棄物(がれき類) | 2,000~5,000円/トン | 建設リサイクル法に基づき、原則として再資源化が義務付けられている。破砕され、再生砕石として道路の路盤材などに利用される。 |
| 鉄筋(鉄くず) | 産業廃棄物(金属くず) | 0~30円/kg (有価物) | 分別して金属リサイクル業者に売却できる場合がある。見積書で「有価物」として処理されているか確認。 |
| 土砂 | 建設発生土(廃棄物ではない) | 6,000~8,000円/㎥ | 有害物質の有無により処分先が異なる。廃棄物が混入しないよう、現場での分別管理が重要。 |
※費用目安は2025年時点のものです(出典:奈良県, 株式会社ニイザト)。廃棄物の処理を委託する際は、マニフェスト(産業廃棄物管理票)が発行されます。これは、廃棄物が適正に処理されたことを証明する重要な書類であり、施主は最終処分の完了が記載された「E票」の写しを受け取り、5年間保管する義務があります。
危険ブロック塀撤去の補助制度
多くの自治体では、地震時の倒壊リスクがある危険なブロック塀の撤去を促進するため、費用の一部を補助する制度を設けています。お住まいの地域に制度があるか、事前に確認することをお勧めします。
自治体による補助制度の例
- 対象となる塀:公道に面していること、規定の高さを超えていること、点検の結果「危険」と判断されること、などが一般的な条件です。
- 補助内容:撤去費用の1/2~2/3程度で、上限額(例:20~30万円)が設定されていることが多いです。
- 注意点:必ず工事契約前に申請し、交付決定を受ける必要があります。決定前に着工した場合は対象外となるため、注意が必要です。
| 自治体 | 対象要件の例 | 上限額(2025年8月時点) | 窓口URL |
|---|---|---|---|
| 横浜市 | 高さ1m以上で道路等に面し、倒壊の危険性があるブロック塀等 | 500,000円 | 横浜市公式サイト |
| 川崎市 | 高さ1.2m超で道路または公園に面するブロック塀等 | 300,000円 | 川崎市公式サイト |
| 大和市 | 道路に面し、安全点検で危険と判定されたブロック塀等 | 300,000円 | 大和市公式サイト |
チェックリスト(発注前/着工前/完了時)
最後に、業者選定から工事完了まで、施主として確認すべき項目をチェックリストにまとめました。トラブルを避け、納得のいく工事を実現するためにご活用ください。
発注者向け確認リスト
| タイミング | 確認項目 | チェック |
|---|---|---|
| 発注前 | □ 見積書に工種別の内訳(解体、運搬、仮設等)が明記されているか? | |
| □ 安全対策(支保工、養生等)の内容と費用が記載されているか? | ||
| □ 建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可を保有しているか? | ||
| □ 自治体の補助金制度の対象か、申請手続きについて説明はあったか? | ||
| 着工前 | □ 近隣への挨拶は、業者が主体となって実施したか? | |
| □ 道路使用許可や特定建設作業届出など、必要な行政手続きは完了しているか? | ||
| □ 着工前の現況(隣家の壁など)を写真で記録したか? | ||
| 完了時 | □ 残存部分に不要なひび割れや損傷はないか?仕上がりは綺麗か? | |
| □ マニフェスト(E票)の写しを受け取ったか? | ||
| □ 最終的な請求額は、見積額と大きく乖離していないか?(追加工事分は要確認) |
まとめ
ブロック塀・擁壁の部分解体は、専門的な知識と技術を要する工事です。費用だけで業者を選ぶのではなく、安全基準や法令を遵守し、適切な施工計画を立てられるかという視点が極めて重要になります。本記事で解説した費用内訳、安全対策、行政手続きの知識を活用し、複数の業者から詳細な見積もりを取り、その内容をしっかりと比較検討してください。
特に、残存部の強度を確保するための仮設(支保工)や、擁壁の排水対策、そしてマニフェストによる適正な産廃処理は、安全で安心な工事に不可欠な要素です。これらの項目について誠実な説明と対応ができる業者を選ぶことが、最終的に財産と安全を守ることにつながります。
よくある質問
- 部分解体と全撤去、どちらが安全ですか? 残存部の安定性・排水が確保できるなら部分解体でも安全です。基準は施行令62条の8および各自治体指針を参照してください(例:福島市「安全安心なブロック塀等」)。
- 見積で必ず確認すべき点は? 工種別内訳、仮設・安全措置(支保工・散水・防音・交通誘導)、産廃処分(品目・数量・マニフェスト)の3点です。「一式」表記のみは避けましょう。
- 高さ・厚さ・控え壁の最低基準は? 高さ2.2m以下、壁厚10~15cm、控え壁は3.4m以内ごとに塀高さの1/5以上など。詳しくは国住指第1130号の点検要領をご確認ください(国土交通省通知)。
- 擁壁を2m超でいじる場合の手続きは? 高さ2m超の擁壁は「工作物」として建築確認申請が必要です。盛土規制・宅地造成の許可や届出も該当する場合があります(盛土規制情報)。
- 工法はどう選ぶ? 開口や切断精度が重要ならウォールソー/ワイヤーソー、近接や振動配慮なら手壊し主体など、周辺環境・残存部の安定で決めます。
- 雨天や豪雨のときは? 背面水圧が上がり崩壊リスクが増すため、雨天中止基準と排水確保(水抜き孔・透水層)を工程に組み込みます。
- アスベスト調査は必要? 解体・改修は原則事前調査が必要です。規模により報告義務が生じます(厚労省 事前調査結果報告システム)。
- 産廃はどう管理する? コンクリートがら・金属くず・建設発生土は分別解体し、電子マニフェストで運搬・処分を管理します(参考:建設リサイクル関係資料)。
- 道路上に車両や資材を置けますか? 道路使用許可が必要です。交通量や歩行者導線により交通誘導員の配置基準も適用されます(例:神奈川県の騒音・振動・作業時間)。
- 補助金は使えますか? 危険と判定されたブロック塀の撤去等で補助がある自治体があります。いずれも交付決定前着工不可が通例です(例:大和市補助制度、横浜市改善事業、川崎市助成金)。
- 工期の目安は? 小規模の上部撤去で1~2日、開口新設や基礎撤去を伴う場合は3~7日が目安です。占用許可・近隣調整により前後します。
- 良い業者の見極め方は? 施工計画・仮設計画の提示、数量根拠のある内訳、許認可・届出の代行、写真台帳やマニフェスト等の証跡提出が揃っているかを確認します。
参考サイト
- 国土交通省:ブロック塀等の安全確保対策について — 国の公式文書で高さ、控え壁など安全基準に関する解説が詳細
- 国土交通省:建築物解体工事共通仕様書(令和4年版) — 解体工事における仮設、安全、産廃処理など実務基準の定本
- 外構エクステリアパートナーズ:ブロック塀解体費用を徹底解説 — 明示的な㎡単価相場(処分込5,000~10,000円/㎡)を示しており、実務に即した費用感がわかります
- クラッソーネ:部分解体は可能?費用相場や注意点 — 部分解体の実例と注意点を扱い、安全性とコストのバランスについて考察されています
初心者のための用語集
- ブロック塀:中空のコンクリートブロックを積み上げた塀。外構の仕切りに使われるが、土圧を受け止める構造ではない。
- 擁壁:盛土や斜面の土圧を支える構造物。鉄筋コンクリートやL型・重力式など種類があり、高さ2m超は確認申請が必要。
- 控え壁:ブロック塀の転倒を防ぐため、直角に設置される補強壁。塀高さの1/5以上突出し、3.4m以内ごとに配置が基準。
- 支保工:解体や施工中に構造物を支える仮設の補強。残存部の安定や崩壊防止のために使う。
- 水抜き孔:擁壁背面の水圧を逃がすための穴。径50mm以上を1m間隔で設置するのが基準。
- 建築基準法施行令62条の8:ブロック塀の高さ・厚さ・鉄筋・控え壁・基礎などの安全基準を定めた規定。
- 宅地造成規制法:盛土・切土や擁壁工事の許可・届出を義務付ける法律。区域指定内では必須。
- 電子マニフェスト:産業廃棄物の処理過程を記録・管理する電子システム。解体時のコンクリートがらや鉄筋処分に必須。
- ウォールソー:ダイヤモンドブレードを用いてコンクリートを高精度に切断する工法。開口部新設などに用いられる。
- 一式見積:工種や数量の根拠を示さず「一式」とまとめた見積形式。追加費用や不透明性のリスクが高い。